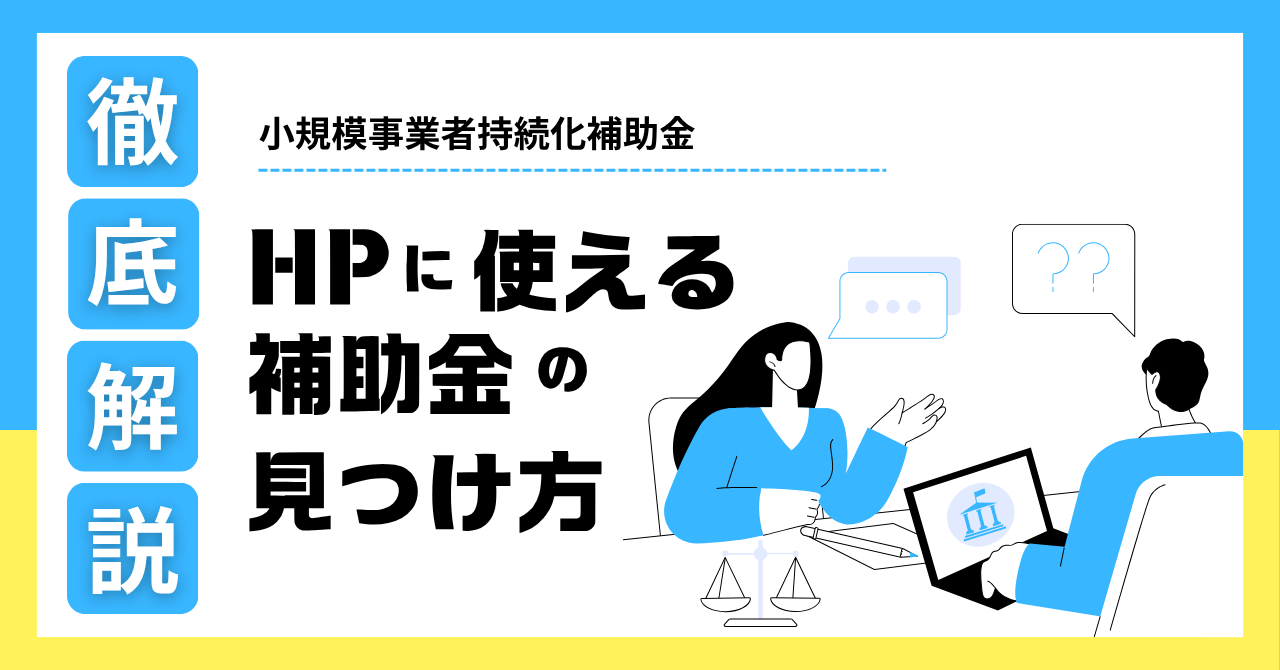本記事は、多くの制作会社で共通して採用されている「一般的なホームページ制作フロー」をベースに作成したものです。制作会社によって工程や作業範囲は異なるため、「一般化された内容」として参考にしてください。
ホームページ制作は、一見すると「作るだけ」のシンプルな作業に見えるかもしれません。しかし、実際には企画・文章・デザイン・構築・テスト・運用という多くの工程があり、1つでも曖昧なまま進めると後の工程すべてに影響が出ます。
本記事では、初めてホームページを制作する方でも理解できるよう、各工程をできる限りていねいに、専門用語をかみ砕いて説明しています。読み終えた頃には「なぜ制作に時間がかかるのか?」「どこに費用が発生するのか?」という疑問も自然と整理できる内容です。
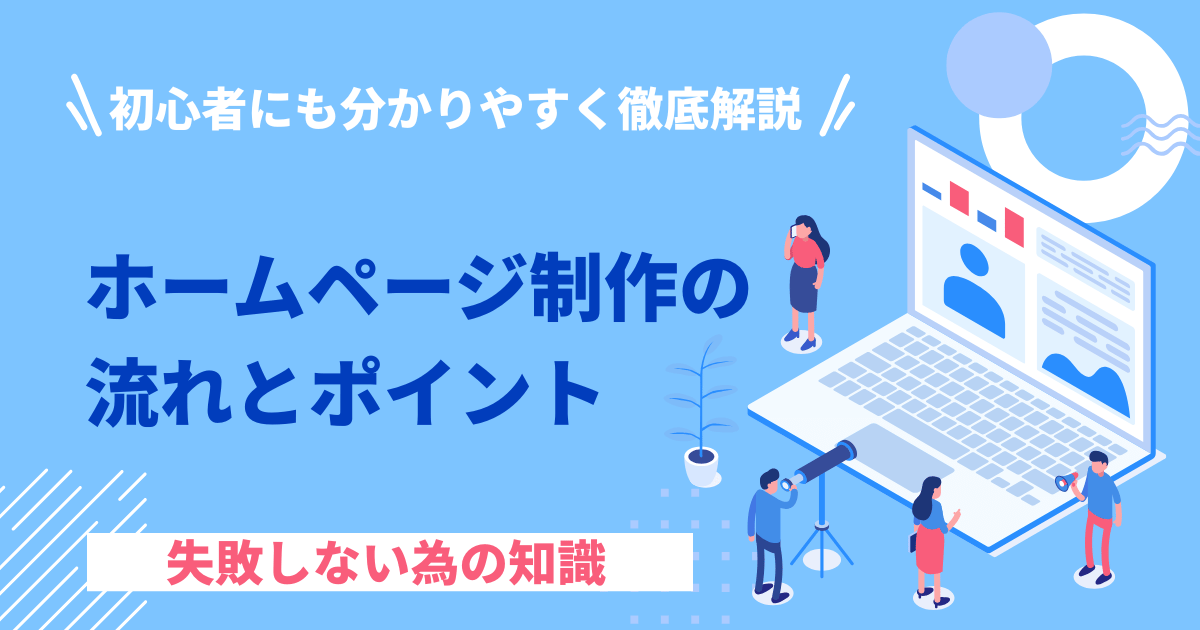
- 1. 1. ホームページ制作の全体像|まずは“全体の流れ”をつかむ
- 2. 2. ヒアリング・要件定義|ここがブレると全工程が狂う
- 2.1. ■ ヒアリングで確認される内容(一般的な例)
- 2.2. ■ なぜヒアリングが最重要なのか?
- 3. 3. サイト構成(サイトマップ)|訪問者が迷わない導線を作る
- 3.1. ■ 一般的なサイト構成例(企業サイト)
- 3.2. ■ サイト構成で大切なポイント
- 4. 4. 原稿制作(ライティング)|ホームページの成否は文章で決まる
- 4.1. ■ 原稿制作で必要な作業
- 4.2. ■ よくある誤解
- 5. 5. デザイン制作|見た目だけでなく“伝わる設計”が重要
- 5.1. ■ デザイン工程の一般的な流れ
- 5.2. ■ デザインで大切なこと
- 5.3. ■ よくあるつまずき
- 6. 6. コーディング・CMS設定(WordPressなど)
- 6.1. ■ 実装で行われる作業の一例
- 6.2. ■ セキュリティ面の注意
- 7. 7. 公開前テスト|細かい修正を徹底する重要フェーズ
- 7.1. ■ 一般的なチェック項目
- 8. 8. 公開後の運用・改善|ホームページは“育てる資産”
- 8.1. ■ 公開後に必要な運用の例
- 9. 9. 制作で起こりやすいトラブルと防止策
- 9.1. ■ トラブル例と予防策
- 9.1.1. ① 目的が曖昧 → 途中でブレる
- 9.1.2. ② 原稿が用意できず、制作が止まる
- 9.1.3. ③ デザインイメージの相違
- 9.1.4. ④ 更新が難しい
- 9.1.5. ⑤ 追加料金が増える
- 10. 10. まとめ|“一般的な制作フロー”を理解することが成功の第一歩
- 11. 【注記・免責事項】
1. ホームページ制作の全体像|まずは“全体の流れ”をつかむ
ホームページ制作は一般的に以下の7つの工程で進みます。
- ヒアリング・要件定義
- サイト構成(サイトマップ)
- 原稿制作(ライティング)
- デザイン制作
- コーディング・CMS設定
- 公開前テスト
- 公開後の運用・改善
※注記:制作会社によって工程の順序、役割分担、作業範囲は異なります。
テンプレート制作の場合は工程が短縮されたり、オーダーメイド制作では工程が増えることがあります。
以下では、それぞれの工程を「初心者でも理解できる言葉」で、かつ「専門家にも通用する深度」で説明します。
2. ヒアリング・要件定義|ここがブレると全工程が狂う
■ ヒアリングで確認される内容(一般的な例)
- ホームページを作る目的(売上・集客・採用・信頼性向上など)
- ターゲット(どんな人に見てもらうのか)
- 伝えたいメッセージ・強み
- 競合サイトと差別化すべきポイント
- 必要なページ数・必要な機能(予約、問い合わせ、地図、ブログなど)
- デザインイメージ(参考サイト)
- 予算・納期の目安
- 更新頻度・公開後の運用体制
■ なぜヒアリングが最重要なのか?
制作工程は「ピラミッド構造」で成立しています。
- 目的・ターゲット →(影響)→ サイト構成
- サイト構成 →(影響)→ 原稿・デザイン
- 原稿 →(影響)→ デザイン
- デザイン →(影響)→ 実装(コーディング)
つまり、最初の「目的のズレ」は、後半になるほど修正が困難になり、費用と時間が倍増します。
よくある失敗例:
「とりあえず作ってほしい」という依頼で始めてしまい、途中で“何を目指すサイトか”が不明確に。
→ デザイン・文章・構成がバラバラになり、目的達成が難しくなります。
3. サイト構成(サイトマップ)|訪問者が迷わない導線を作る
ヒアリング内容をもとに、どんなページが必要か整理する工程です。
■ 一般的なサイト構成例(企業サイト)
- トップページ
- サービス紹介
- 料金表
- 会社概要
- よくある質問
- お問い合わせフォーム
- ブログ(お知らせ)
■ サイト構成で大切なポイント
- “必要なページだけ” を明確にすること
- ターゲットが知りたい順番で情報を並べること
- サービス導線(問い合わせ・申込みへの導線)を分かりやすく設計すること
- SEOを考える場合、キーワード設計もここで行うこと
注意:ページ数が多ければ良い、というものではありません。
“訪問者が迷わない” 情報設計が何より重要です。
4. 原稿制作(ライティング)|ホームページの成否は文章で決まる
ホームページの文章は「ただ書くだけ」ではありません。 心理学・マーケティング・SEO・読みやすさ・信頼性を考慮しながら設計されます。
■ 原稿制作で必要な作業
- 事実情報(会社情報・サービス内容)の整理
- 競合との差別化ポイントの明確化
- ターゲットに合わせた言葉選び
- 読みやすい構成(短い段落・結論ファースト)
- SEOのための適切なキーワード挿入
- ファクト(根拠)を裏付ける写真・数字の整理
補足:原稿制作は「お客様が書く場合」と「制作会社が書く場合」があります。
どちらが担当するかで工数も費用も大きく変わるため、事前確認が重要です。
■ よくある誤解
- 「文章は後で考える」 → これはNG。文章が無いとデザインが作れません。
- 「長い文章が良い」 → 読む人は長文を読みません。要点が大切。
- 「専門用語を多く書けば信頼される」 → 初心者には伝わりにくく、離脱の原因に。
5. デザイン制作|見た目だけでなく“伝わる設計”が重要
■ デザイン工程の一般的な流れ
- ワイヤーフレーム(構成図)の作成
- トップページのビジュアル作成
- 下層ページデザイン
- スマホ版の調整(レスポンシブデザイン)
■ デザインで大切なこと
- 企業イメージに沿った色・フォント
- 読みやすい余白設計
- ユーザーが迷わない視線誘導
- 信頼感を高める写真選定
■ よくあるつまずき
- 「イメージと違う」問題 → 参考サイトを共有すると防げます。
- 写真の品質差 → 良い写真はホームページの印象を大きく改善します。
- スマホデザイン軽視 → 実際の閲覧の7割前後はスマホです。
6. コーディング・CMS設定(WordPressなど)
デザインが決まったら、実際にブラウザで表示できる形に組み立てていきます。
■ 実装で行われる作業の一例
- HTML/CSS/JavaScriptによるコーディング
- WordPressテーマの設定・調整
- プラグインの選定・構築
- フォーム設定・メール送信の確認
- サーバー設定(SSL・DNS)
- アクセス解析(GA4・Search Console)の設置
補足:「WordPressは自分で更新できる」と言われますが、テーマの構造や設定次第で編集難易度は大きく変わります。
■ セキュリティ面の注意
- WordPressアップデート
- プラグインのメンテナンス
- サーバーの安全設定
- バックアップ体制
これらは制作会社によって「保守契約に含まれる範囲」が異なるため、事前確認が必須です。
7. 公開前テスト|細かい修正を徹底する重要フェーズ
■ 一般的なチェック項目
- 表示崩れ(PC/スマホ)
- リンク切れ
- フォーム動作確認
- 画像の読み込み速度
- 誤字脱字
- OGP設定(SNSシェアの見た目)
- SEO基本設定(タイトル・ディスクリプション)
注意:公開前チェックは「制作会社だけがやるもの」ではありません。必ず依頼者自身による確認も必要です。
8. 公開後の運用・改善|ホームページは“育てる資産”
ホームページは、公開して終わりではなく、公開後からが本番です。
■ 公開後に必要な運用の例
- 記事更新(SEO向け)
- お客様の声や実績の更新
- サービス内容の変化に伴う調整
- アクセス解析をもとに改善
- フォーム離脱率の改善
- 写真の入れ替え
- セキュリティ対策
改善を継続することで、問い合わせ数の増加・採用効果・認知向上など、事業への利益が段階的に蓄積されていきます。
9. 制作で起こりやすいトラブルと防止策
■ トラブル例と予防策
① 目的が曖昧 → 途中でブレる
→ 初回ヒアリングで「目的・ターゲット・達成したいこと」を言語化する。
② 原稿が用意できず、制作が止まる
→ 原稿制作を制作会社に依頼する選択肢を検討。
③ デザインイメージの相違
→ 参考サイト3つを共有すると認識が揃いやすい。
④ 更新が難しい
→ CMS(WordPressなど)の編集範囲を事前確認。
⑤ 追加料金が増える
→ 見積もりは「含まれるもの/含まれないもの」を明確化。
10. まとめ|“一般的な制作フロー”を理解することが成功の第一歩
ホームページ制作は、
ヒアリング → 構成 → 原稿 → デザイン → 実装 → 公開 → 運用
という流れで進むことが一般的ですが、制作会社によって詳細が異なります。
重要なのは、
- 目的を最初に明確にすること
- 依頼者と制作会社の認識を揃えること
- 公開後の運用を見据えて作ること
この三点が揃っていれば、ホームページは「作って終わり」のものではなく、事業の成長を支える重要な営業資産になります。
【注記・免責事項】
- 本記事の内容は「一般的な制作工程」を元にしており、制作会社によって工程・価格・手順は異なります。
- 技術仕様、CMS(WordPress等)の設定方法、セキュリティ対策などは各制作会社の方針により大きく異なる場合があります。
- 本記事は特定の制作会社の方法を推奨するものではありません。
- SEO効果、問い合わせ増加などの成果は保証されるものではなく、運用や市場環境によって変動します。